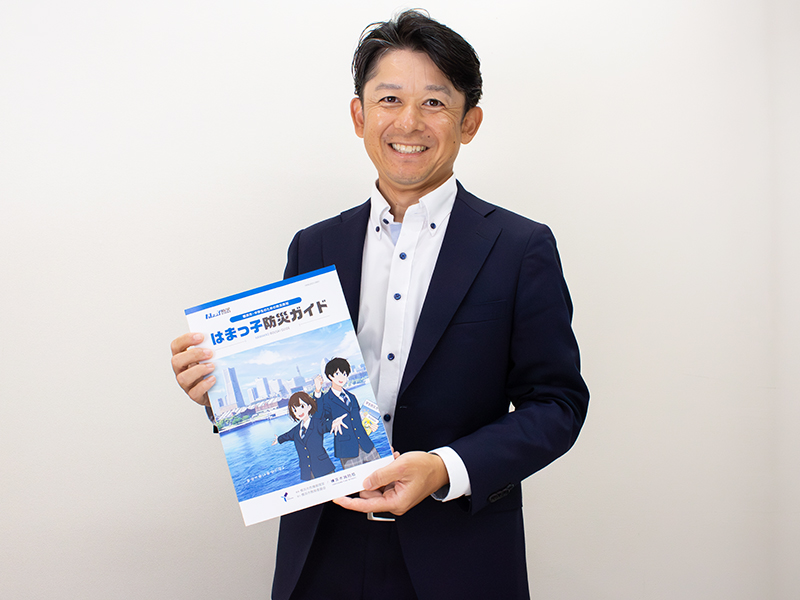※このページに書いてある内容は取材日(2025年07月25日)時点のものです
「はまっ子防災プロジェクト」で横浜の街を守る
私は株式会社ペガサスで「はまっ子防災プロジェクト」のプロデューサーとして働いています。株式会社ペガサスは、防災用品の製造や販売、防災教室、防災プロジェクトの運営などを行う防災事業と、さまざまな企業や、自治体から依頼を受けて、ウェブサイトやパンフレット、ポスターなどを作る制作事業を手がけています。会社では、印刷物のレイアウトやデザインをパソコン上で行う編集DTP(デスクトップパブリッシング)を担当する人、ウェブサイトを作る人、動画撮影をする人など、計13人の社員が働いています。
「はまっ子防災プロジェクト」とは、神奈川県横浜市に住む全ての中学生が3年間を通してわかりやすく防災を学ぶことを目指して、2022年から横浜市と一緒に行っている防災プロジェクトです。企画、制作、運営は私たちが行い、運営費は企業から協賛をいただいて成り立っています。学習の軸となるのは、横浜市監修の「はまっ子防災ガイド」という教材です。全3章から構成されており、授業内で視聴する3話構成の動画「はまっ子防災アニメーション」と合わせて、1章を1年次に、2章を2年次に、3章を3年次に使用する想定です。
「自助」「共助」の力を身につけてほしい
「はまっ子防災ガイド」は総合的な学習の時間で使われたり、避難訓練の時間に使われたりするなど、学校によって使用方法はさまざまです。1、2年次で使用する章には理科単元、3年次の章には道徳単元に関連する内容を盛り込み、いろいろな方向から防災が学べる仕組みにしました。先生方が授業で扱う際は「先生用ガイド解説書」で下調べの時間を短縮できるように工夫しています。
そのほかにも、住んでいる場所の災害リスクを調べられる「はまっ子防災MAP」や、例えばコンタクトレンズや薬など、自分のために自分で選んだ備蓄品を収納できる「はまっ子防災BOX」、使い方を練習できる「非常用トイレ」といったアイテムがあり、合わせて6つのアイテムが横浜市の中学1年生に配布されています。市の中学1年生全員が対象で、約150校、26,000人に配布されています。
中学生のみなさんにはこのプロジェクトを通して、自分で自分の身を守る「自助」の力と、周りの人たちと助け合う「共助」の力を身につけてほしいと思っています。そうすることで、いざというときに自分たちの住む街を守れるようになるのです。
はじまりは防災ライト
もともと、私たちの会社では、内蔵のマグネシウム電池と水の化学反応を使って点灯させる防災ライトの開発と販売を行っていました。どこかで災害が起こったときには、防災ライトを買う人が増え、売り上げが伸びました。しかし、時間がたつにつれて災害への関心が薄れてしまうと、防災ライトをわざわざ買おうという人は減ってしまいます。
そこで、もっと多くの人に商品を知ってもらうために横浜市の防災イベントに参加しました。イベントに参加して、防災に関心があるのは年配の人がほとんどで、小学生や中学生などの若い人たちは防災にあまり関心を持っていないことに気がつきました。横浜市は人が多く、にぎやかで楽しい街です。でも災害が起こったとき、人口の多さは重大な被害を引き起こす原因にもなります。そのようなことにならないためには、若いうちから防災の知識をしっかり身につけておくことが大切です。そう考えた私は、防災ライトも防災への知識も広められるようにと「はまっ子防災プロジェクト」を企画しました(なお、プロジェクト当初は防災ライトを配布していましたが、現在は非常用トイレに変更しています)。
私は兵庫県神戸市出身で、高校1年生のときに阪神・淡路大震災を経験しています。当時の私は防災に全く興味がなく、知識もなかったのですが、周りの悲惨な状況を見て「防災についての知識はあったほうがよい」と実感しました。この経験も、プロジェクトを立ち上げる理由の一つとなりました。
関わる人全員にメリットがあるプロジェクトを
「はまっ子防災プロジェクト」は2020年から動き出しました。まずは横浜市の市民向けに配られている防災の啓発冊子を参考に、「これを中学生に伝えるにはどうすればよいか」ということを考えて、企画や構成を練りました。そして、でき上がったものを横浜市に持っていって、「こんなプロジェクトを始めませんか」と提案しました。
横浜市には防災の知識が蓄積され、協力してくれる企業は地域に貢献でき、中学生は防災の学習が受けられるという、関わる人全員にメリットがある企画を認めていただき、プロジェクトがスタートすることが決まりました。
そのときプロジェクトに携わっていた社員は4人でした。ガイドの詳しい内容やアニメーションのストーリー決めは、基本的に私中心で担当していたのでとても大変でしたが、「形にすれば横浜市の防災教育に貢献できる」との思いで一生懸命頑張りました。ほかの社員たちにも「いつか人の命を救うかもしれないプロジェクトだよ」と声をかけるなど、モチベーションを高く保って取り組んでもらえるよう工夫しました。
中学生が関心を持ってくれる教材を作る
中学生に防災の知識を広めるためには、興味を持ってもらえるような工夫をする必要がありました。そこで思いついたアイテムの一つが、「アニメーション」です。「はまっ子防災ガイド」だけで学習を進めるのではなく、映像も使って災害の恐ろしさや実際の現場の空気感をわかりやすく学ぶことができる仕組みにしました。
ときには、中学生のみなさんからもらったアンケートから、もっとよいプロジェクトにするためのヒントをもらうこともあります。例えば、「もっといろいろな情報を知りたい」という意見を取り入れ、文字をさらに小さくしてより詳しい情報を「はまっ子防災ガイド」に載せることにしました。
こうして、さまざまな工夫を重ねた「はまっ子防災プロジェクト」に中学生のみなさんが興味を持ってくれたときは、達成感があります。ある保護者の方から、「子どもがうれしそうに持って帰ってきました」とのお言葉をいただいたときは、とてもうれしかったです。
大変なのは協力してくれる企業を集めること
プロジェクトを進める中で一番大変なことは、「協賛」という形でプロジェクトに協力してくれる企業を探すことです。そのために、毎日違う企業に「はまっ子防災プロジェクト」についてお話ししています。締め切り間近は、多いときは10時、13時、16時にアポイントメントを入れて、一日に3件は企業を訪問するのがルーティンになります。相手に伝わりやすいようにプロジェクトについて細かくプレゼンテーションしたり、生徒のみなさんからのアンケート結果を見せたりして、熱を入れて説明しています。特に、その企業が「はまっ子防災プロジェクト」に協力するメリットや、その企業だから作れる防災誌面について強調してお伝えします。
みなさんさまざまな理由で協賛を決めてくれていますが、一番多いのは「地元である横浜に貢献したい」という理由です。協賛してくれる企業は、1年目は63社、2年目は114社、3年目は163社、4年目の今年は181社にまで増えました。
一人一人のやる気を引き出せるようなリーダーを目指す
現在「はまっ子防災プロジェクト」に携わる社員は10人に増えました。横浜市での実績を踏まえて、同じ神奈川県の藤沢市や東京都品川区など、ほかの地域にも同様のプロジェクトが広がっていて、さまざまな地域に役に立つものをゼロから作り上げるこの仕事に、とてもやりがいを感じています。
プロデューサーとして、「はまっ子防災プロジェクト」のチームをまとめる上で心がけていることは、自分から率先して仕事をすることです。リーダーが一番仕事を頑張ることで、周りの社員が「私も頑張ろう」という気持ちになってくれます。
最近はマネジメントも行っています。マネジメントとは、会社にいる社員全員の力を最大限に引き出すために、働きやすい環境を整えたり、誰にどの役割を分担すればよいか考えたりする役割のことです。ただ指示を出しているだけでは、社員とのよい関係はつくれません。一人一人に楽しく前向きに仕事をしてもらうこと、会社を好きになってもらうことを大切にして、日々、社員とのコミュニケーションをとっています。動画を見たり本を読んだりして、よりよいマネジメントができるように勉強している最中です。
活発で好奇心旺盛だった子ども時代
子どものころは、周りの大人たちから活発な子と言われていました。運動神経がいいほうで、運動会に力を入れたり休み時間に中心となってドッジボールをしたりしているような子どもでした。中学校でやる体力測定では運動部の主将レベルの同級生に交ざりながらも、総合結果で毎回必ず銅賞はもらっていたことを覚えています。
小学3年生から中学1年生までは野球をやっていました。全てのスポーツに共通するような基本動作を習得しただけではなく、コミュニケーション能力や不利な状況でもめげない精神力、挨拶や会話のマナーなどを教えてもらいました。これらのスキルは、社会で働くようになってからも役に立っています。
野球以外で今につながっていることは、一つ一つの物事を興味深く捉えて、自分なりに調べる習慣です。関西出身だからかもしれませんが、何事も細かく分析して「いかに面白い笑い話にするか」を常に考えていました。いわゆる「ネタを作る」というものです。このテクニックは「はまっ子防災プロジェクト」で、中学生に興味を持ってもらえるような表現や構成を考えるときに役立ちました。子どものころに何気なくやっていたことで身についた力が、大人になった今にも生きていると感じています。